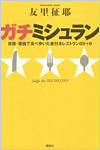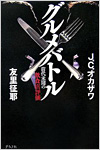- 固定リンク
-
店訪問
|
- 2010年10月23日(土)|
未だミシュランが手元にありません。昨日も買うのを忘れておりました。
東京版で実売3万部前後(全国ですよ!)、京都・大阪版で実売10万部弱と推測される2010年版ミシュランガイド。(どのような根拠で推測したかなど詳しくは来週に)
初年度ミシュラン東京版(2008年版)の実売数が20万部以上と推測されるだけに、わずか3年で桁落ちどころか8割減。京都・大阪版の2年目(2011年版)も大きく数字を落とすことは簡単に予想できることであります。
私は初年度のミシュランフィーバーの時、いずれ普通のグルメガイドと同じように数万部に落ち着くと予想しましたが、わずか3年でその予想が当たるとは思いませんでした。
全世界100国前後でのミシュランガイドの総販売数が100万部といわれております。単純に計算すると1国でわずか1万部。ミシュランといえどもグルメガイドの実売はこんなものなんですね。
読者の方からの情報によりますと、一昨日のロオジエにナレ氏が来ていたそうです。奥のテーブルで、足を組んで斜め座りで食べていたとか。生まれつき行儀が悪いと言ってしまえばそれまでですが、彼の経歴などを見てみればさもありなん。成り上がりの放送作家と同じく、中身は食通を装う俄グルメなだけなんですね。
店評価ブログにフレンチ「オギノ」と鰻の「かぶと」をアップしております。ぜひお立ち寄り下さい。
さて週間食日記であります。
月曜日
昼:コリドー街の生パスタ屋
夜:銀座の高額割烹
先週に続いて生パスタ屋へ行ってしまいました。今回はオイルたっぷりのトリュフパスタ。でも、香りがあるかどうかは別にして、トリュフらしきものは結構入っておりました。
夜は蕎麦を出す高額割烹。とは言ってもコース主体です。接待使用で客は喜んでおりました。
火曜日
昼:麻布十番のイタリアン
夜:銀座の鮨屋
仕事で近辺まで行って、気になっていたイタリアンへ飛び込みました。シェフが替わってから初訪問のカンテサンスと同じ系列の店であります。
ランチの最低コースが2800円と驚きの高さ。ドアを開けたらスタッフがビックリした顔をしていたので客が少ないんだなと直感したのですが、なんと客はゼロでした。この不景気に麻十で3000円近い値付けでは、客が入るはずがありません。でも料理は結構良かったので、暇があったら夜にでも訪問してみるのも良いかもしれません。
夜はCPが良いと評判の高額鮨屋。しかし不景気からか以前のような盛況さは感じませんでした。四谷の満席偽装寿司屋「三谷」の情報を偶然出会った知人の連れの有名鮪仲卸社長から得ることが出来ました。
水曜日
昼:銀座の天麩羅屋
夜:神楽坂の鍋屋
取引先を連れて初訪問。急に揚げ物が食べたくなったからです。食べログで調べての訪問。最近の店なのでしょうか、若い揚げ手(主人)のようでしたが、夜にしっかり食べて評価をしてみたいと思います。
夜は会社関係者と久々のねぎま鍋。価格に見合った鍋でした。
木曜日
昼:難波の蕎麦屋
夜:神戸の寿司屋
出張で大阪へ。時間的な問題で駅近くのショッピングモールのような建屋の蕎麦屋へ入って珍しいのでカレーつけソバを頼んでしまいました。揚げた野菜もついていましたが、蓮根など固くて噛み切れない。最悪でした。
夜はミシュラン2つ星の寿司屋。ビールグラスが魚臭かった。
金曜日
昼:神戸の長田流そばめし屋
夜:鉄板焼き屋
仕事のついでに訪問したのが最近流行という長田料理。「そばめし」と言って、そばとご飯を鉄板で焼いたものが名物のようです。何とも言えない食後感。
土曜日
昼:品川のオイスターバー
夜:内食
出張の帰りに、急に思いついて駅構内のオイスターバーへ。オープン当初の混雑がウソのような落ち着いた店内でした。小さなオイスターをいくつも頼んで結構な支払いとなってしまった。
日曜日
昼:近所の蕎麦屋
夜:白金のお好み焼き屋
知り合いの家族と久々に大箱お好み焼き屋へ。以前は小さな地下店で、モデル出身の主人が自ら焼いていたのですが、大箱になってまったく見かけなくなりました。
たこ焼き、お好み焼きなど食べましたが、ワインも3000円で持ち込めてまずまず満足しました。
- 固定リンク
-
自己宣伝
|
- 2010年10月22日(金)|
今朝のTVで検事総長の記者会見の模様を見ました。本人はやめるつもりはないようですが、それは自身の性格からかもしれません。彼は往生際が悪い人ではないでしょうか。それは彼の髪型を見れば一目瞭然。いまどき、これほどはっきりした
一九分け
をしている人が生き残っているとは思いませんでした。
左側頭部の髪の毛を不自然に伸ばして右側へ流すように垂らしているのですが、トップがこんな偽装工作を続けているようでしたら、検察の再生は難しいのではないか。まずは検事総長自ら「一九分け」と決別するべきと考えます。
昨日はミシュランガイド京都・大阪・神戸版の発売日だったんですね。昨晩ある和食店で食べていて思い出したのですが遅かった。
この3年間、東京版含めてすべて初日に購入していた友里。日本でミシュランにこれほど執着していた人間が買い忘れるほどですから、もう誰も買っていないのではないか。
新版の実売数は更に落ち込むと思うのですが、先日出版業界に関係するという読者から、ミシュランの返品率など具体的な数値の情報をいただきました。
驚くべき実売数の激減と返品率の増大なのですが、ナレ氏ふくめミシュランは「刷り数」しか発表していないんですね。見栄張って沢山刷っても、これほどの率で返品されたら(実売が減少)、事業として成り立たないとおもうのですが、何を考えているのやら。
詳しくは来週にでもブログで取り上げてみたいと思います。
さてその来週でありますが、10日間弱、ネット環境(時差も)が異なる所へ移動の予定です。ブログの更新、掲示板への回答、そしてメール返信がタイムリーにできないかもしれませんが、出来るかぎり頑張りますのでご容赦ください。何処へ行くか、想像がつく方も多いかもしれませんね。
さて昨日発売の「週刊新潮」で久々に友里のコメントが掲載されております。
「焼き鳥」より「焼肉」と副題がついた
「菅直人」美食日誌
という46ページから3ページにわたる特集記事。47ページ最後の部分から48ページにかけて3言ほどのコメントですので、お読みいただければ(立ち読みは勘弁)幸いです。
このコメントは先週末ころに電話取材を受けたのですが、実は経済月刊誌からも連載のイメージで同じようなオファーがありました。その月刊誌とは
ZAITEN(財界展望)
という月刊誌でして、すでに第一回目の校了を終わっている12月号(11/1発売)からスタート、不評で打ちきりにならなければ半年連載が続く予定であります。
よくある経済月刊誌と違って、政財界ベッタリではない検証精神ある編集の経済月刊誌ですので、これを機会にぜひお買い上げの上お読みいただければ幸いです。
- 固定リンク
-
店訪問, 御礼
|
- 2010年10月21日(木)|
応募をされていた方はイライラされたのではないでしょうか。7月に「月刊めしとも」で募集させていただいた
友里征耶とのディナー権
でありますが、昨晩港区のあるフレンチで開催させていただきましたことをここに報告させていただきます。
参加されたのは4名(偶然か全員女性でした)の読者と編集部から1名、友里入れて計6名でありました。19時から23時過ぎまで、4時間以上と自分ではあっという間に感じたディナーでありました。
この模様は来月発売の「月刊めしとも」に報告の形としてちょっと掲載されるようです。しっかり開催したということをご確認いただければ幸いです。
店内で「友里」という単語は禁句にしていただきましたが、内容から他の客にしられることを避けるため珍しく個室を予約。他客ウオッチングを趣味にしている友里としましては珍しいことであります。昨晩その店にどのくらい客が入っていたか、どれだけ興味深い客(見ていて)がいたか、がまったくわからなかったのが残念でありましたが、同席していただいた方のおかげで普段よりも美味しく料理をいただけました。(シェフ、リップサービスなので深い意味はありません)
持ち込んだワインは出席者のヴィンテージを考慮しての2本。
‘75 ヴィユー シャトー セルタン
‘72 リシュブール グロ
でありまして、どちらも予想以上に美味しかった。72年のリシュブールは12年前にボーヌ近くのワインショップで購入してハンドキャリーで日本へ持ち帰ったもの。果実味が充分でそれは美味しゅうございました。セルタンも思ったより良い状態で驚きました。
最近はレストランへ滅多に持ち込まなくなったのですが、やはり古いワインは家で飲むよりレストランで飲むのが一番。
以前のブログでワインの持ち込みルールについて書きました。店と客はイーヴンの立場ですから、店にも持ち込み客にもメリットあるよう良好な関係を保ってこれ以上
持ち込みオッケーの店が減らないよう?
客側の配慮が重要だと私は考えます。
独特の風土を持つ名古屋地区(このブログを見て下さい)を除く持ち込み希望の人へのお願いであります。
話は変わりますが、J.C.オカザワのディナー権、もう開催したのでしょうか。彼が案内する下町の店(寿司屋?居酒屋?)へ応募された方がいらっしゃるのでしょうか。昨晩の参加者から
居酒屋レベルにわざわざ応募する人がいるはずがない
なんて過激な発言も飛び出しておりました。
まあ人それぞれ嗜好や考えは異なりますから、応募がまったくないということはあり得ないと思いますが、世間から疑われないように早めの開催(今すぐでも遅いですけど)を発表した方が良いでしょう。
「月刊めしとも」から友里がクビにならず、また肝心の「めしとも」が廃刊にならなければ、また機会がありましたらこのような企画をしてみたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。