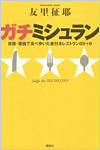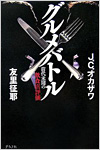今週半ばにいつもの環境に復帰いたしまして、夜の銀座の街並みの暗さや恵比寿ガーデンの陸の孤島化に驚きました。
デパ地下の終業時刻をはやめたようで、仕入れが少ない。売れ残りを防ぐためでしょうが、各店で揃える商品はかなり量と種類を絞っているのではないでしょうか。
営業時間の短縮だけではなく取扱商品の減少。大震災前と比べたら、食品だけではなく他の商品においても
売り上げは半減しているのではないか
と私は思ってしまいました。節電による営業自粛と大震災による消費マインドの低下が主因でありますが、この節電はいつまで続けるのかについて世に予測が出ておりません。
計画停電はひとまず4月下旬で終わり、夏場に復活すると言われていますが、それはあくまで
現状の節電を持続する
という前提ではないでしょうか。マスコミは停電の有無ばかり問題にしますが、節電の持続についての考察が抜け落ちています。
私が予想するに
本来ならこのまま何年も節電を続けなければならない
のではないかと。
動く歩道を止めただけではなく照明もかなり落とした恵比寿スカイウオーク。夜は歩く人がいなくなったと聞きました。恵比寿ガーデンはまさに
陸の孤島化
となってしまった。
大震災の影響ではありませんがこの恵比寿ガーデン、賞味期限が切れたからか地下の飲食街は私の好きだったトンカツ屋に加えて、最初から客入りが厳しかった焼鳥屋まで閉店しております。
デパ地下では、やはり私が贔屓にしていたヘルシー食品(電子レンジで調理できる)と、その多店舗嗜好から当初より将来を不安視していた「スープストック トーキョー」が消滅していた。
出来ては消えを繰り返すこのスープチェーンでありますが、値付けの高さに加えて、スープものに限定したもともとのコンセプトに無理があり、多店舗には向いておりません。
毎日飲めるコーヒーならまだしも、種類があるとはいえ似たようなスープを毎日飲めるものか。しかも高い。
こんな店を雨後の竹の子(最近は貴重なようです)のように増殖させてしまっては、自ら希少性を下げてしまうこともあり、飽きられるのは必定であります。牛丼チェーンのように、客単価を400円以下にしなければ、この手の店の増殖は無理だと私は考えます。
話はそれてしまいましたので元に戻します。
このまま節電を続けて営業自粛していたら、客商売の店の多くは壊滅してしまうのではないでしょうか。
背に腹はかえられません。そのうち節電を捨て、通常の営業状態へ戻す店(特に大型店舗)も出てくるのではないでしょうか。そうなると、
計画停電の早い復活
になってしまいます。
もうアカン政府は夏場から罰則規定(100万円)を盛り込んだ節電強制法を施行するとも聞きました。この節電放棄を防ぐ狙いがあるのでしょうが、国民として従う前に
東電役員の私財を義援金へ(清水社長の昨年の年収は8億円近くあったとの報道がアメリカでありました)
東電役員の私宅を避難民へ提供
東電社宅を避難民へ開放
東電OB社員をやめさせ避難民を東電グループで採用
といった策がとられなければ、納得する国民は少ないのではないでしょうか。
帰宅して貯まった郵便物の中の東電からの通知を見て私はひっくりこけました。?
検針が出来なかったので、先月分の使用量で請求する
とあるではないですか。この節電にみんなが協力している東電管内で、
前月並みの電気を消費しているような非国民がいると思っているのか。
どの家庭どの企業でも、何割も使用電気量は落としているはずです。
普通の頭の経営者なら、検針できないのは己の事故による混乱が原因ですから
今月は請求せず検針してからまとめて精算
もしくは
とりあえず半分(8割でもいいぞ)の請求で、検針後精算
とするのが、迷惑かけている客へのせめてもの誠意のあらわしではないでしょうか。この会社の
殿様感覚
がなくならない限り、国有化は逃れられないと私は考えます。