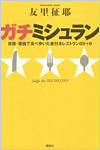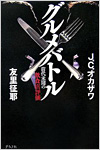昨日の友里ブログにより、冷却が必要な原子炉のため外部から海水や水を注入したら、その入れた量だけ原子炉の外へ垂れ流さなければならない理由がおわかりいただけたと思います。?
再循環ポンプが動かない現在、仮に外部から水を入れることが出来ても、圧力容器などの容積は有限であります。
冷却は自動車のラジエターを見ればおわかりになると思いますが、冷却水か冷却される媒体のどちらからを
循環
させなければなりません。停留していたら熱を逃がせません。
冷却水は熱源を冷ましますが、それによって冷却水自体は温まってしまうからです。その温まった冷却水では冷却効果が期待できないのは理工系の方でなくともおわかりいただけると思います。
よって毎日何十トンも注入している「真水」は、しっかり原子炉の外(つまり外部である建屋や敷地内)へジャジャ漏れさせなければ、炉心の冷却は出来ないのであります。
圧力容器が壊れた結果注入した真水が自然に外部放出できるようになったのか、自発的にクローズドサイクルを破って外部へジャジャ漏れにしたのかは、神、もとい東電と政府のみ真実を知るところでありますが、どちらにしても溶融したと言われる燃料棒を直接冷やした汚染真水が刻々と注入した分だけ外部へ放出しているのは間違いありません。そうでなければ、炉心を冷却できません。
そこで大きな問題。昨日から溜めてあった低濃度汚染水を海へ放出しているとの報道があります。
増え続ける高濃度汚染水(炉心を冷却するため注入した真水)を貯蔵するスペース確保のため、今まで溜めていた低濃度汚染水を海へ流した方が結果的には実害は少ないという、政府と東電の究極の判断なのでしょう。
高濃度の汚染水が溢れかえるよりマシだろう
との計算でしょうが、彼らはこの先、つまり1ヶ月先、半年先、いや一年先のことを考えているのでしょうか。
溶融した燃料棒がこの数週間で冷却される、もしくは圧力容器の破損を直し緊急冷却システムが稼働して冷却水が炉心を循環するようになれば、外部からの真水注入は必要なくなりますから、高濃度汚染水のジャジャ漏れもなくなるでしょう。?
しかし昨日のブログにも書きましたが、ジャジャ漏れの原因である圧力容器かそれに繋がる配管の破損を、この環境(放射線量が高い)のなか補修(溶接など)することは不可能のはず。破損の場所を見つけることも難しいと考えます。
複雑な配管配置であり、炉心が冷えていない段階では格納容器や圧力容器に近づけないからであります。
また、肝心の再循環ポンプを確認することも難しいのではないか。原子炉建屋の底に位置していると記憶するこのポンプ、そこへたどり着くだけでもかなりの時間を要してしまい被曝量が多くなるからです。たとえたどり着いたとしても、そこで点検や修理の作業をすることが容易であるとは思えません。
よって私はこのまま数ヶ月、いや年単位での外部からの注入、そして外部への流出という、オープンサイクルでの循環冷却を継続するしか策はないとネガティヴに考えてしまうのです。
そうなると、溶融した燃料棒に直接触れた高濃度汚染水が毎日増産(毎日500トン注入されているらしい)されていくことがおわかりいただけると思います。
今朝のTVで、ピットからの高濃度汚染水の海への流出は止まったとの報道がありましたが、これから毎日増え続けるこの高濃度汚染水をどう処理するつもりなのか。
メガフロートに溜めるつもりでしょうが、メガといっても容量は有限であります。
直ちに溶融した燃料棒を冷却できない現状では早晩、高濃度汚染水は溢れてしまうことになるのです。正に
一難去ってまた一難
なのですが、後手に回っている政府や東電には、そこまでの対策は現段階で考えられないのかもしれません。
不安を煽るつもりはありませんが、
圧力容器やその系統配管の破損箇所を特定できるのか
その破損箇所を修理することが出来るのか
圧力容器外部への冷却水流出を止められるのか
再循環ポンプの場所へたどり着けるのか
循環による冷却システムはいつ回復できるのか
オープンサイクルの外部注入式冷却(高濃度汚染水垂れ流し式)しかないとしたら、冷却に何年かかるか?
そろそろ政府や東電は、真実を開示する時期にきていると私は考えます。